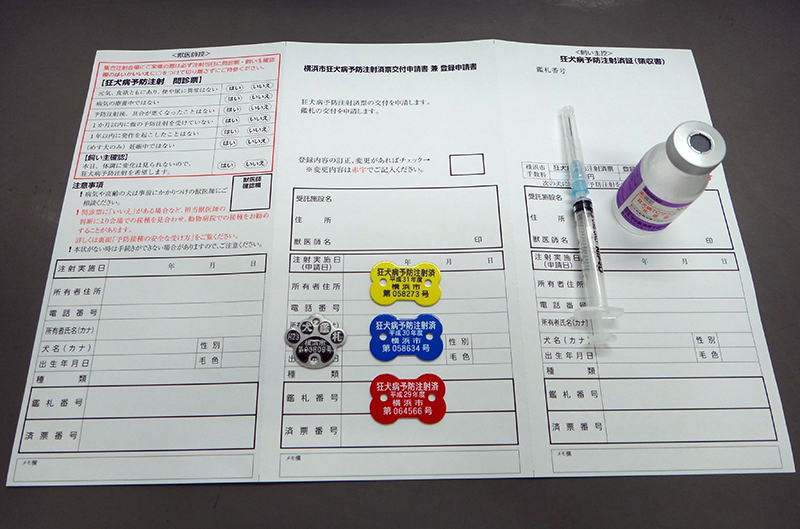フィラリア

犬が蚊の吸血により感染してしまう病気が犬フィラリア症です。
吸血により感染したフィラリアの幼虫は犬の体内を動き回り脱皮を繰り返し最終的には心臓へとたどり着き親虫となって子虫を生み続け、子虫を血液中に放出し、これが再び蚊の体内に入り他の犬へと感染が拡大して行きます。
フィラリア成虫は15cm~20cmぐらいのヒモ状の線虫で心臓に至る血管内や心臓内で悪さをします。心臓が小さな動物ほどフィラリアの影響は深刻そうですが、どのサイズであろうとも感染は起こさせたくないものです。予防には内服タイプに錠剤・チュアブル、滴下式のスポットオン、年に1度の注射タイプと各種ございます。ご家庭の状況や手間を考えて選択しましょう。
予防期間は注射の場合を除きおおよそ5月から12月までの8ヶ月間を想定しています。